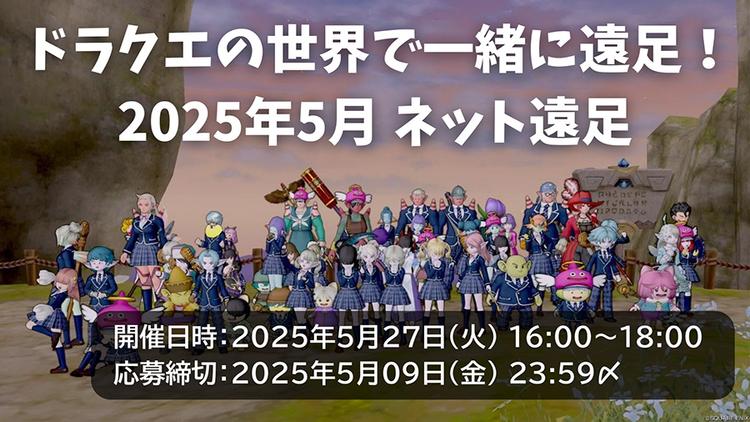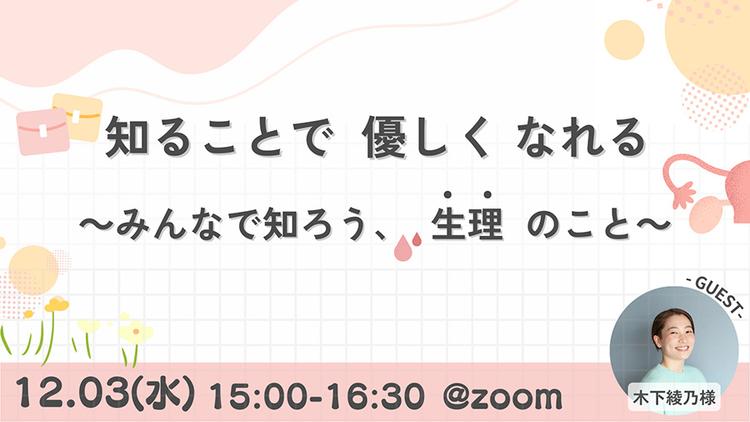※このブログは天王寺キャンパス1年生、福澤優喜さんと上野蒼太さんに書いてもらいました。
2023年10月28日に開催したキャンパスフェスティバルの準備~当日の運営を経て、私たちが自身の学びに繋がったことをご紹介します。
※1 各キャンパスで開催される通学コースと通学プログラミングコース生が参加するフェスティバル。出し物の企画・運営は全て生徒自身が行います。
はじめに、班長を務めた私・福澤優喜が、班長の経験を経てどんな学びや気づきを得たのかをお伝えします。皆さまがN/S高に入学して挑戦できることの参考の1つになればと願います。
今年度のキャンパスフェスティバルでは、主に「デザイン(装飾)の担当」「メインエリア(カジノゲームやプレゼンテーション大会)の企画」「体を動かすアクティビティエリアの企画」の3つの部門に分かれて運営しました。
その中で私は、当日ゲームを行う「ヘブンルーム」(※2)の班長を務めました。
※2 天王寺キャンパスにある部屋の名前。

ゲーム企画で、私の班は、目隠しをしてソフトスポンジでバトルをする「気配切り」と、イントロクイズを実施しました。
準備段階で、まず私が班長として最初に行ったことは、企画実施までの大まかな流れや日程を決めることです。
最初に大まかにでも流れを決めておいた結果、チーム全体の方向を揃えたり、目的意識を共有したりすることができました。
次にやったことが連絡手段の確立です。
N/S高ではSlack(角川ドワンゴ学園で使用しているコミュニケーションツール)を活用しているのですが、私の班でもみんなが使い慣れているSlackを連絡ツールとして諸々の連絡を行いました。
連絡手段を確立させることでメンバー全員がどこに連絡すればいいのか迷うことなく、円滑なコミュニケーションの実現につながりました。
チームで動くための基盤を作ったあとは、最初に決めた日程通りにミーティングやタスクを進めていきました。
ミーティングを重ねていくうちにさまざまな課題にぶつかり悩むことがありました。
特に私は、大人数での合意形成をとる時に、全員の意見を受け止め、それをどのような形に落とし込めばいいのか分からなかったことが最も大きな悩みでした。
例えば、今回のゲームでは、飴玉をチップとし、遊びながら集めた飴玉で他のゲームを行ったり、飲み物やお菓子へ交換したりする「カジノ制度」を導入しましたが、最初は否定的な意見も多く、導入するか否かの合意形成を行う際には、さまざまな意見が飛び交いました。
しかし、私は全員のアイディアを上手くまとめきれず、全員の混乱を引き起こしてしまいました。
そういったときは、進捗などは一旦無視して立ち止まり、俯瞰した状態で課題点を言語化したり、解決案を模索したりしていました。
先輩方から合意形成のコツなどを教えていただき、メンターからも、「君しかできないと信じてる」という言葉をもらい、とてもモチベーションにつながりました。
そうして課題一つひとつと丁寧に向き合ったことで、最後までメンバー全員の意見を拾いながら走り切ることができました。
これらの経験から、私は今回の班長の経験を通して課題と“丁寧に“向き合うことの大切さや、複数人でプロジェクトを進行する時に大切な意識や行動について学ぶことができました。
そして何よりも、班のメンバーに限らず色んな人とたくさん関わり合いながら一つのイベントを作り上げて、それを成功させたのがとても嬉しかったし楽しかったです!
導入に悩んでいたカジノ制度も結果とても面白く、参加した方々は子どもから大人までチップの飴を増やすことを楽しんでいた様子が印象的でした。
キャンパスを後にする際、「楽しかった!」や「来年もキャンフェスに来たいです!」などの声をかけていただきました。
今後も、キャンフェスに限らずいろいろなイベントでたくさんの人と関わって何かを成し遂げていきたいと思います。
続いて、天王寺キャンパスに週5(※3)で通っているN高1年の上野蒼太が、キャンフェス実行委員長の経験でどんな学びや気づきを得たのかをお伝えいたします。
※3 N/S高の通学コースはWeekday Course(週5)・3Days Course(週3)・1Day Course(週1)の3つの通学スタイルを用意しています。
今回私はキャンフェス実行委員長となり、キャンフェスを盛り上げ、成功させることができました。
私がなぜ実行委員長になったかというと、自分で何かを作り上げたかったからです。
以前までの私は何をやるにも続かず、中途半端な状態で諦めてしまうことが多く、自分で何かを成し遂げたり、作り上げることができない性格でした。
そんな性格を変えたくて、実行委員長になりました。

私の課題は、圧倒的なスキル不足でした。
もともと私にはリーダーシップがなく、全員の前で何かを伝えることも苦手でした。
なので、準備期間が始まってからの約1ヵ月間は実行委員同士の連携ができず、協力し合える状態にできませんでした。
私はこの課題から、気づきを得ました。
私に、1人で行動しようとする癖があったことです。
そのままでは私自身の成長にも繋がらないので、「私”たち”で何かを作り上げる」ことを目標にしました。
このような気づきを通して、私は課題を解決するために、メンターや先輩方に相談をしまくりました。
そうすることで、私に足りなかったスキル、意識などが明確化され、そこに集中した努力を積み重ね、自身に定着させることができました。
その結果、残りの準備期間では少しずつ実行委員同士での連携を上手く取り合えるようになり、協力し合う場面も多く見えました。
各企画を遂行するグループが協力をして別の企画を手伝ったり、当日もカフェテリア付近の外装や、写真スポット用のバタフライアートの設置などは、実行委員全員で連携して行うことができました。
これらの経験から、私は人に相談することで課題を明確にすることの大切さを学ぶことができました!
そして何よりも、実行委員全員で作り上げていく過程が楽しかったと感じています。
この準備期間の楽しさが、キャンフェス当日の面白さに繋がったと感じています。
終了後、実行委員のメンバーからは「とても楽しかった」や「緊張で倒れそうだったけど、今は達成感でいっぱいです」「他のキャンパスと共同でキャンパスフェスをしたい!」「来てくれた人が楽しいって思えるキャンフェスにしたい」といったポジティブな声が多くありました。
また、来場者の方々がキャンフェス終了時、「楽しかったよ」、「面白かったし、来年も来ようかな」と言ってくれて、とても嬉しかったです。
実行委員全員で大変だった準備期間を乗り越えて良かったと改めて思いました。

今後も、キャンフェス以外でも実行委員長になり、大きなプロジェクトを進行していきたいです。