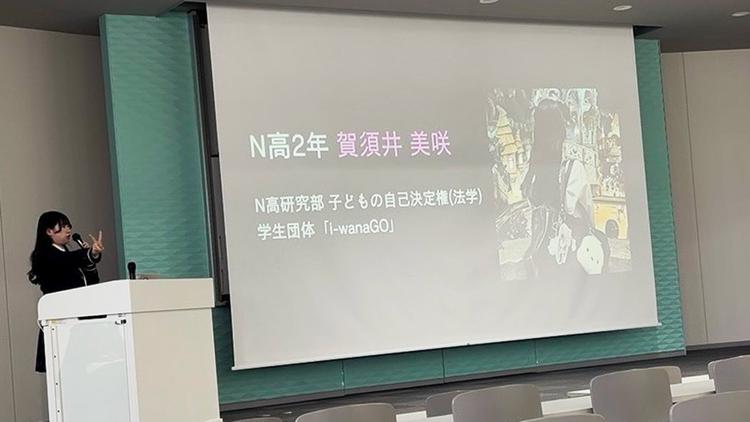※このブログは投資部1年生、都賀遼太郎さんに書いてもらいました。
はじめまして、N高1年の都賀遼太郎と申します。
今回ご縁がありましてこのブログを書かせていただくことになりました。
拙い文章にはなりますが、読んでいただけると嬉しいです。
■東証Arrowsって?
東証Arrowsは、日本最大の証券取引所である東京証券取引所の一部です。この場所では、投資家に対してリアルタイムの市場情報を提供するとともに、上場企業が的確な情報開示を行うためのサポートを行っています。
この度、私たち投資部の部員は東証Arrowsでマーケットセンターの見学をし、東京証券取引所の職員から、東京証券取引所の歴史や役割についての講義を受けました。
■マーケットセンター見学
私は、マーケットセンターに関してはテレビで映っている姿しか見たことがなく、事前知識がほぼない状態でした。
入口を抜けると見えてきたのはこちら。

大きい!!!
ガラス張りの外壁の上部にはニュース映像などでもお馴染みの円形のモニター(チッカー)が!
参加した部員からも、「テレビで見たままだ!」などの歓声があがっており、みんな熱心に写真におさめていました。
案内してくださった方によれば、この建物がガラス張りになっている理由は、取引の仕組みや状況が誰にでもわかるようにするため(市場の透明性)、そして取引が平等にかつ正しく行われていること(公平性)を象徴しているからだそうです。
この中では、東京証券取引所の社員がコンピュータの画面を見て、異常な値段や数量の注文、急激な値段の変動がないかどうかを監視しているとのことですが、私が訪問した際にはなんとワンオペでの監視を行っていました。
この点について、職員の方に質問したところ、新型コロナウイルスの影響で大人数での業務が困難になり、その結果としてこのような業務形態になったとのことでした。
■講義

施設の見学が終わり、私たちは東京証券取引所の職員の方から、最近の証券市場・取引所の役割について、そして上場企業に関する講義を受けました。その講義では、世界での東京証券取引所の競争力や海外投資家の日本株保有比率、市場区分の見直しに関するメリット・デメリットや経緯などについて、さまざまな情報を学ぶことができました。
特に注目すべきは、日本株の株式保有比率で海外投資家が30.1%(保有比率では首位)と多くの割合を占めており、そのためIR資料などの英文開示のニーズが非常に高い点です。
しかし、プライム市場(※1)上場会社において、定性情報や注記事項、セグメント情報の英文開示実施状況が50%程度にとどまっていることに驚きました。
さらに、現状ではプライム市場の約半数、スタンダード市場(※2)の約6割の上場企業がROE(※3)8%未満、PBR(※4)1倍割れといった数値が見受けられ、経営者の資本コストや株価に対する意識改革が必要であることもわかりました。
このような状況が続くことによって、海外証券市場の更なる成長の中で、東京証券取引所の競争力や魅力が損なわれ、経済停滞が進む可能性があることを考えると、私たち若者がその必要性を発信し、議論していくべきだと感じました。
※1 2022年4月4日(月)の市場区分の再編により運用が開始された東京証券取引所(以下、東証)の株式市場の一つ。再編された東証の市場には、プライム市場のほかに「スタンダード市場」「グロース市場」があり、プライム市場は3つの市場のうち、最も上位の市場。
※2 公開された市場における投資対象として一定の時価総額(流動性)を持ち、上場企業としての基本的なガバナンス水準を備えつつ、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上にコミットする企業向けの市場。
※3 ROE(自己資本利益率)は、Return On Equityの略称で、和訳は自己資本利益率。投資家が投下した資本に対し、企業がどれだけの利益を上げているかを表す重要な財務指標。ROEの数値が高いほど経営効率が良いと言える。
※4 PBRとは、株価純資産倍率(Price Book-value Ratio)のことで、株価が割安か割高かを判断するための指標。純資産から見た「株価の割安性」。株価が直前の本決算期末の「1株当たり純資産」の何倍になっているかを示す。
■感想
見学と講義を通じて、物事の常識を積極的に疑い、自ら行動することの重要性を学びました。
さらに、他の投資部員との意見交換ができたことは、何よりも有意義であったと考えています。
これからも投資部での活動を続ける中で、異なる立場の方々から意見を聞き、金融経済について自らの見識を深めていきたいです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
・投資部紹介ページ
https://nnn.ed.jp/about/club/investment/