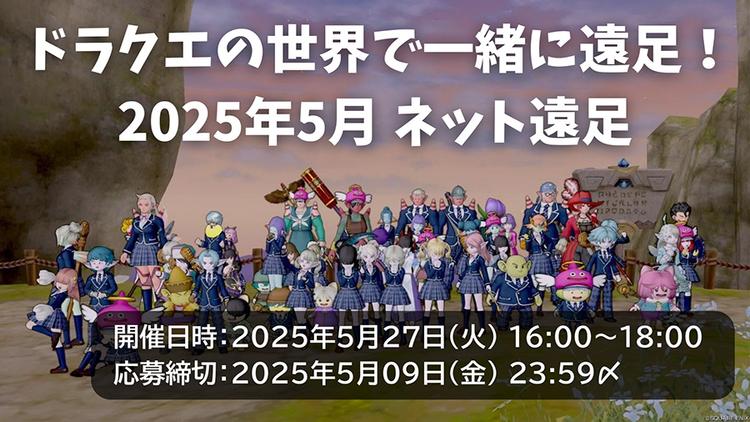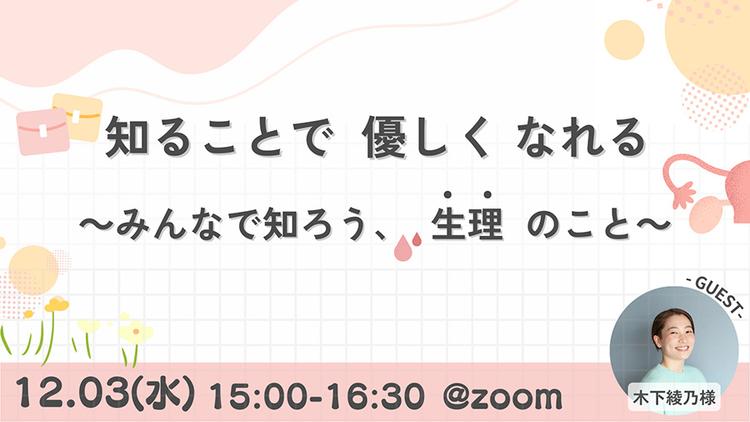11月13日(金)に、立憲民主党 枝野幸男代表を講師としてお招きした特別講義が実施されました。
今回は、「若い頃の失敗と乗り越え方」をテーマにしたご自身のお話を皮切りに、生徒から寄せられた幅広い分野にわたる政治的な質問に、政治部特別講師の三浦瑠麗氏との対談を通してお答えいただく形で進行しました。どんな質問にも、即座にしっかりとしたご意見を返してくださり、参加者にとって非常に勉強になると同時に、自分ごととして考えさせられる瞬間もあり、あっという間の1時間でした。
※YouTubeで枝野幸男代表の講義の全編をご覧いただけます。
「【N高政治部】立憲民主党 枝野幸男代表 特別講義(高校生のための主権者教育)」
※ここからの内容は、政治部部員の生徒に書いてもらいました。
私は地方在住のため、今回の講義にはビデオ会議ツール「Zoom」を介して参加しました。実は枝野代表は、私が政治部の入部応募をした際、お話を聞いてみたい政治家としてお名前をあげさせていただいた方だったため、登壇が決定したときからこの日を本当に楽しみにしていました。
まず最初に、枝野さんからこんなテーマに沿ったお話をしていただきました。「若い頃から今までのご自分の人生にひきつけた失敗の経験といかに人間はそうしたものを乗り越えられるか。」
このテーマを聞いて少し困ったという枝野さん。
というのも、失敗を失敗として引きずらないタイプだからだとおっしゃいます。

さまざまな、「失敗」だと捉えることができるような経験も、結果的に良かった、と思うことができているからだそうです。
失敗したことやできないことにこだわるよりは、別のところにプラスがあるはずだと思うことで乗り越えてきたのだとご自身を振り返られました。
志望校に進学できなかったことや英語が苦手であることを打ち明けながら、自分にできないことがあっても、得意な人と補い合うことで解決できるということを教えてくださいました。
「失敗は100%が失敗ではない。そのときに得られた財産があるはず」という言葉も印象に残りました。
続いて、枝野代表と政治部特別講師の三浦瑠麗氏による対談へと移ります。事前に生徒から寄せられた質問をベースに、いくつかのテーマに分けて対談が行われました。
ここからは個人的に印象に残った部分や、「なるほど!」と思った部分をご紹介します。

■SNSの問題
SNSの発展に伴い、匿名での誹謗中傷が増えている中、否定的な意見をぶつけられがちな政治家として枝野さんはどう考えているのかという質問に対し、「Twitterのリプライは見ていないし、ミュート(※)も積極的にかけているので否定的な意見は基本的に読んでいない」とおっしゃったので驚きました。
※1 ミュートとは…特定のアカウントや特定のキーワードを含むツイートを非表示にする機能
「見る価値のある反対意見を拾う責任はあるが、ただの罵詈雑言のようなマイナスなリプライは見ないのが一番。政治家でなければもっと見る必要はない」とのことでした。
また、政治でSNSなどでの誹謗中傷を解決できないのか、という問いについては、言論表現の自由などに絡んでくるため難しく、風潮作りや司法などで解決していくことが必要であると訴えられました。
SNSや掲示板に書き込みをする人々が、個人の特定が可能であるということをもっと認識すれば、誹謗中傷も相当程度落ち着くのではないか、とも。
私はよくエゴサーチをして感情を左右されてしまいがちなので「政治家でなければもっと見なくていい」という言葉に惹かれました。
■シルバーデモクラシーと若者
「介護や年金などはお年寄りの話、ではなく、若者のための制度だ」
少子高齢化社会において、有権者における高齢者の割合が大きくなり、政治への影響力が増す「シルバーデモクラシー」をどう見ているかという問いに対し、枝野さんは強く主張されました。
「年金制度の充実は、若い世代が(親世代の老後の生活費を気にせずに)好きなことをできるようにする制度」であり、「介護の充実は、若い世代が親や祖父母の介護でやりたいことができなくなるというケースを小さくするための制度」である、と。
政治ではその認識に齟齬があり、それを説得しなければ若い人の政治に対する意識やシルバーデモクラシーを変えることにはつながらない、とずっと考えてこられたそうです。
また、若者に対する政治戦略としては、「(政治家が)単なる普通のおじさんおばさんであることを知ってもらう」ことを意識しているそう。
枝野さんご自身は普段から歌を歌うほどアイドルがお好きで、アイドルに関するお話をたくさんするようにしているとのこと。そうすることで、遠い存在に思っている政治家を身近に感じてもらい、政治にも関心を持ってもらう機会になるのではないかと期待しているそうです。
共通項を見つけてもらうことで若者が他人事に感じていた政治に親近感を持つという考え方は、私が個人的に普段から考えていることと一致し、大いに納得しました。
さらに、政治的知識が未熟な若者の投票を疑問視する声に対しては、「分からなければ、分からないことを前提に、分かる範囲で判断する。それが民主主義である」と言い切られ、選挙はすべてを理解した状態で投票しなければならないのではないかと考えていた私にはまさに目から鱗な考え方でした。
■教育
高校時代、合唱部での活動に力を入れていたという枝野さん。政治とは一見関係ないように思えますが、意外なところで役立ったというエピソードが。選挙に出た際、発声方法がプラスとなり声がかれにくいという利点となって返ってきたというのです。そのため自身の選挙では声をからしたことがないとのこと。このことから、「人生何が役に立つか分からないけれど、今関心のあることを一生懸命やることが大切。それが何かの形で返ってくるのではないか」という気づきを得たそうです。
また、学校の勉強に関しては、都心と地方での選択肢の差や生徒間での学習状況の進み具合などを危惧した上で、「一つの学校の中にいろんな選択肢があることが教育にとっては重要」という考えを示されました。
私自身、N高生としてかなり選択肢の多い学校で日々学んでいるわけですが、個人が選択できるというのは自分に対して大きな責任がともなうと実感しています。だからこそ多様な選択を多くの学校で可能にすることは必要で、プラスなことなのではないかと思いました。
■環境問題とゼロエミッション(※2)
※2 ゼロエミッションとは…排出物の有効利用により発生量を減らし、廃棄物をゼロに近づけようとする理念
2050年までに「温室効果ガス実質ゼロ」を目標に掲げた菅内閣。これに対し、枝野さんは立憲民主党としての姿勢をこのように語ってくださいました。「2050年までの綿密なロードマップを作成する予定はない。新エネルギーや蓄電に関する技術革新が必要となってくるここから30年先の技術が分からない状況で作っても、それは嘘でしかないから」
菅総理が「2050年に温室効果ガスゼロ」という目標値を掲げたことは評価しつつも、その目標達成に向けて原発を使うのであればそう高いハードルではない、と指摘。原発を辞めながらゼロを目指すことこそ難しいと。しかしながら、枝野さんはエネルギーの問題としてはほぼ解決済みの話だとおっしゃいました。新再生可能エネルギーの能力は高く、原発を辞め、火力を大幅に削減してもエネルギーは足りるそうで、30年もあれば十分整理できるとのことです。
課題として、誰が送電線を引くかということが挙げられますが、国が引き受けることと、蓄電をしっかりすることさえできれば可能な話なのだそう。
未来のこと、それも30年先のことはは分からない、予測が立たないという認識を明確にしたうえでお話をしてくださり、非常に納得しました。送電線に関するお話も大変勉強になりました。
■働く人や親への支援
子育て支援については、サービスを非常に安く、あるいは場合によっては無料で提供することで行なうのが有効だというお考え。補助金を支給するよりも、学費を免除するなどさまざまな公共サービスを提供していくほうがいいのではとおっしゃっていました。
また、長時間保育所で預かるようにすべきで、昼間の時間帯しか保育所で預からないというのは時代遅れだと思っているそうです。そのためにかかる費用に関しては利用者に一定の負担があってもいいと思う、とも述べられました。
個人的にこの考えに関しては、保育士の待遇改善も併せて論じるべきなのではないかと思いました。働き方が多様化している中で変化していく必要性もあると思いますが、子どもの気持ちは?などと考えさせられる部分もありました。
■所信表明について
前回のオリエンテーション講義(※3)では、菅総理の所信表明に枝野さんが苦言を呈したことが議題として挙がり、双方の価値観や考え方は実は似通っているのではないか、という点について考察しました。今回はそのことについて、枝野さん本人からの説明をいただけるまたとないチャンスでもありました。
※3 前回の講義はこちらからご覧いただけます「【N高政治部】三浦瑠麗 特別講師 オリエンテーション講義」
「確かに、自助努力にウエイトを置いてきた時代はあるが、途中で方針転換した。2005年あたりに間違っているなと気づき、東日本大震災のときに確信を持った。自助努力だけではどうにもならないというときのために政治があるということを、もっと強く意識しなければならないというふうに変わった」と、件の発言の裏にある真意について語ってくださいました。
その上で、「どちらが正しいかということではなく、どちらが良い結果についながりやすいかという視点での選択が必要ではないか」と提言。他の国々でも、競争よりも支え合うことをしっかりやった方が結果につながっていると枝野さんは見ています。
人間なので考えが変化することは当たり前なのですが、政治家であっても、方針転換していくということがあるのだなと驚いたと同時に、それもまた社会を良くするために大切なことなのだと感じました。
最後は生徒の質問コーナーでさまざまな疑問にお答えいただき、講義が終了しました。
以上の内容は、個人の主観により切り取り、抜粋している内容となります。他にも講義に参加した政治部部員のN高生が「note」で記事を書いていますので、そちらも読んでいただけると嬉しいです。
【N高政治部】枝野幸男さんの特別講義の内容と感想をN高生目線からお届け!
https://note.com/takeharu_n/n/n2cf39e8d8311
[N高政治部]枝野代表×三浦瑠麗氏 みんなの質問コーナー