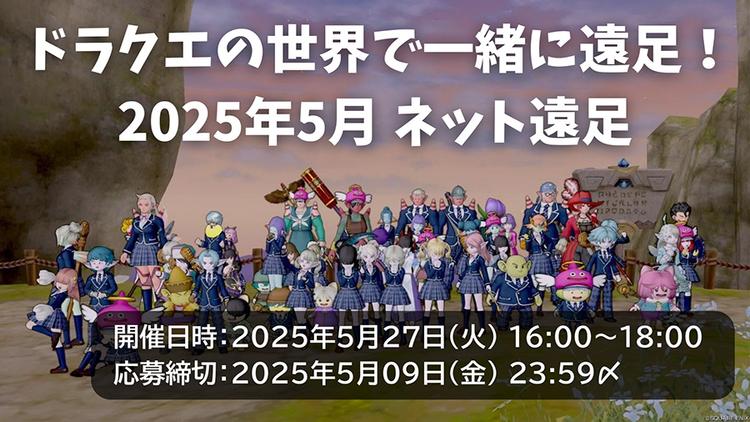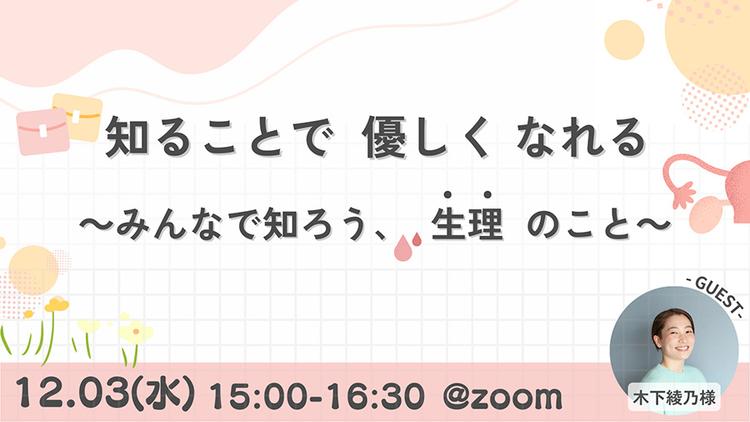2025年5月19日、N高等学校・S高等学校・R高等学校(以下、N高グループ)の投資部と政治部が『投資部×政治部 合同リアル特別講義』を実施しました。今回のテーマは「中高生も一緒に考える、いま話題のあのニュース。あなたは賛成? 反対?」として、生成AI、円安、トランプ大統領の政策という3つのテーマについて議論が行われました。
講師は、投資部特別顧問の村上世彰氏と、政治部顧問の川邊健太郎氏。実際のお金で株式投資に取り組む投資部と、主権者教育として政治家と交流し、政治に関する理解を深める政治部。それぞれの活動で学びを深めてきた部員の生徒に加え、講義に応募した一般の学園生たちが参加し、経済や社会のリアルな課題についてお二人の意見を聞きました。
この記事では、合同講義に参加した生徒たちの感想や気づきをもとに、当日の様子を振り返ります。
※講義のアーカイブは以下のURLからご視聴いただけます。
https://www.youtube.com/watch?v=QaJFjb0Lz_8
テーマ1:生成AIについて
生成AIについて、会場では村上氏と川邊氏を含め賛成が圧倒的多数を占め、オンラインアンケートでも賛成87.5%、反対12.5%という結果となりました。
川邊氏は生成AIを人類の発展史の中で捉え、肯定的な立場を示します。
「人類は長い時間を経て現在の繁栄を築き、身の安全や食の安全など様々な安心を手に入れました。これは生物学的な進化の側面もありますが、むしろ文明的な発展によってこのような安心や繁栄を手に入れることができたのです」と川邊氏は述べました。
特に産業革命によって苛烈な肉体労働から解放された人類が、今度は頭脳労働からも解放されつつある時代が来ることを指摘し、「これを現在だけの視点で反対するというのは、人類が発展してきた歴史を考えると疑問に思います。これまでの長い間に人類が行ってきた技術文明の発展としてのAIを受け入れ、個人が頭脳面でもエンパワーメントしていけばいいのではないでしょうか」と主張しました。
川邊氏は続いて、過去の技術革新への反対運動を例に挙げます。「ラッダイト運動という有名な事例があります。手で機織りを行っていた時代に、産業革命によって自動で機織りを行う機械が現れた際、職人たちがその機械を破壊したのです。また、自動車が出現した時には馬車を操作していた人々がロビー活動を行い、馬車より速い自動車の製造を禁止する法律を一時的に制定しました」と歴史を振り返り、「これらの反対運動は結局無意味であったことを歴史が証明しています」と結論づけました。
村上氏は生成AIに賛成しつつも、「取り残されているような感覚があります」と率直な感想を述べました。川邊氏とのLINEのやり取りで、ChatGPTの回答をコピーで送られてきた経験を紹介したところ、川邊氏は「現在はChatGPTにDeep Research(推論を使用して大量の情報を統合し、複数ステップのタスクを完了するAIエージェント)という機能がある。高額だが、この機能に月3万円を支払えば、私が答えるのと大差ない回答が得られる」とAIの能力向上を実感していることを語りました。
生徒からは就職活動でのエントリーシート作成にAIを使うことについて質問がありました。川邊氏は企業によって対応が異なることと前置きし、「LINEヤフーのようにテクノロジーを活用して新しい価値を生み出していく会社では、AIを使用した上でどのような成果を出してくれるのか、新たな課題に対して従来では不可能だった解決をどのように実現してくれるのかという使いこなし方を評価します」と答えました。
反対派の生徒からは、「人間にしかできないことがAIによってできるようになってしまうと、人間としての価値が損なわれるのではないか」という倫理的な観点や、「2027年には現在のAIよりさらに発達したAGI(Artificial General Intelligence、汎用人工知能)が生まれ、AI自身の意見が生まれるようになってくることが怖い」という将来への懸念が示されました。
川邊氏はこれらについて、「AIが怖いのではなく、人間が怖いのです」と指摘しました。「例えば核の理論が分かった時も、その核の理論や物質は昔からあったわけです。それを活用して核爆弾を作って広島と長崎に投下したのは人間です。人間の方がはるかに怖い」と述べ、技術そのものではなく、それを使う人間の問題であることを強調しました。
生成AIの負の側面として、フェイクニュース問題も議論されました。村上氏は実際に自分の名前と声を使った投資詐欺の被害に遭っていることを明かし、「私を名乗る人物が投資詐欺を行っています。『投資をすれば確実に利益が出る』などという内容を、私の声にそっくりな音声で語る動画が存在しています」と具体的な被害を紹介しました。
川邊氏は「社会の進化がテクノロジーによって加速しすぎています」と言及し、特に高齢者がテレビやラジオが全盛期の時代認識でSNS上の情報を判断してしまう危険性を指摘しました。
テーマ2:円安について
円安については会場で賛否が半々に分かれ、オンラインでは賛成42.1%、反対57.9%という結果となりました。両顧問とも反対の立場を示しました。
村上氏は現在の円安状況を「2年前は1ドル120〜130円でしたが、一時160円まで上昇し、現在は145円程度の水準にあります」と説明し、「多くの方が生活の苦しさを感じるようになりました。円安になると輸入物価が上昇するため、円は強い方が良いと考えています」と述べました。
さらに長期予測として、「将来的には極度の円安になり、1ドル1,000円になる可能性もあると考えています。それほどこの国は脆弱な状況にあります」と発言し、「数十年後の1ドル1,000円説は私が時折唱えているものです」と説明しました。
その理由として人口減少と国力の衰退を挙げ、「人口は減少し続け、国力が弱くなれば、当然円安が進行するでしょう。スーパーインフレも、5年後には来ないかもしれないが、30年後にはなっているかもしれない」と分析しました。
川邊氏は円安問題を構造的な観点から分析しました。「自国通貨が強いことは多くのメリットがありますし、強くなければ立ち行かない構造も日本には一部存在します」と前置きし、特に電気料金問題を重要視しました。
「東日本大震災以降、原発が停止しており、発電には化石燃料まで使用しています。石油や天然ガスが発電の大部分を占め、これらは輸入に依存しているため、円安になると電気料金が上昇し、国民の生活が苦しくなり、産業にも大きな影響を与えます」と具体的な影響を説明しました。
川邊氏はまた、輸出産業の競争力について指摘をしました。「真に価値のある商品であれば、円安でも円高でも売れます。おそらくドル安やドル高に関係なく、iPhoneは売れ続けるでしょう。日本が輸出する商品がコモディティ(他と差別化されていない商品)に近いもの、例えば自動車のようなある種のコモディティ商品に偏っていることが問題です」と述べました。
生徒からは日本の内需と外需の割合について質問がありました。「現在の日本の外需の割合は約28.6%で、他国と比較してかなり低い水準にあります」という指摘に対し、村上氏は現実的な見解を示しました。
「これからの内需が強いはずがありません。まず人口が減少しています。しかし川邊さんがおっしゃるように、優れた商品を海外で多く販売することが重要です。日本経済はもう誰が率いても非常に困難な状況だと思っているので、外需に頼りながら円安になって外需が伸びる方が可能性として大きいと思っています」と述べ、外需依存が続く可能性を説きました。
川邊氏は日本がまだ世界に対して競争力を持つ分野として、「一般消費者向け商品を製造する機械、つまり商品を作るための工業製品において、引き続き市場シェアの高い企業が数多く存在します」と指摘し、さらに「化学合成素材などの素材分野」も挙げました。
特に注目すべきは、コンテンツ産業です。「いわゆるIP(Intellectual Property、知的財産)と呼ばれる分野、例えばアニメは圧倒的な競争力を持っています。現在、コンテンツやIPの輸出額は約4.7兆円に達し、日本の半導体は競争力が低下しましたが、半導体の輸出額5.7兆円とほぼ差がなくなっています。鉄よりもIPの方が多く輸出している状況です」と説明しました。
テーマ3:トランプ大統領の政策について
最後のテーマであるトランプ大統領の政策については、会場では反対が多数を占めたものの、オンラインでは賛成60%、反対40%という結果となりました。両顧問は揃って賛成の立場を示しました。

川邊氏は「反対してもトランプ氏は聞き入れないでしょう」と現実的な観点から賛成理由を説明しました。「そのような人に反対し続けることは、コストがかかり不毛です。実行してもらい、うまくいくものもうまくいかないものも、トランプ氏自身に体感してもらえば良いのではないでしょうか」と述べました。
また、トランプ氏の戦争に対する姿勢を評価し、「少なくとも戦争を助長させようとはしていません。戦争に興味があるような姿勢ではないため、この点は評価しています」と述べました。
生徒から関税政策について質問が出ると、村上氏は具体的な数字を示して説明しました。「アメリカは中国に対する輸出額が日本円で約20〜30兆円、中国からは70〜80兆円程度の輸入超過となっています。アジアから大量に輸入しています」と説明しました。
関税の効果について、「そこに関税をかければ、その分の税収を得ることができます」と示しました。
そしてトランプ氏の税制改革について、「関税で得た資金により税金を廃止し、国民の生活を楽にするもの」と説明し、「少なくともトランプ氏は『3期目はやらない』と言っています。この1〜2年は自分の人気が落ちても構わないわけです。その間に好きなことやらせてくれ、自分は中国に怒ってるんだ、何故50兆円も取られなきゃいけないんだという感覚は私はよく理解できる」と述べました。
生徒からは政府の効率化についても質問があり、川邊氏は「日本はもっと小さな政府になり、歳出削減を行うべきだと長年主張しています」と述べました。
村上氏も「国家公務員を17年間務めた経験から申し上げると、公務員や官僚は比較的効率的で、人数も少ないのです。問題があるのは地方です」と現場経験に基づく見解を示し、「地方に権限を移譲したからといって効率化するとは限りません」と述べました。
さらに川邊氏は「トランプ氏の自国ファーストな政策によって新たな争いが起きるのでは」という視聴者からの懸念に対し、「争いは起こるでしょう」と断言した上で、「争いを起こさせない仕組み、話し合う仕組みの再構築が必要です」と説きました。
最後に国際関係と防衛について議論が展開されました。村上氏は「私は非常に平和主義的な考えを持っています。平和主義的であったからこそ、この国はお金を使わずに成長できました」と自身の立場を明確にし、「防衛費は削減すべきだと考えており、アメリカ軍が撤退しても自国でできる範囲の防衛で十分だと思っています」と述べました。
川邊氏は「新しい戦い方に対応したコストのかからない防衛方法」の重要性を指摘し、「サイバー攻撃や、AI時代の到来により兵器も進化し続けています。また、ドローンの登場により戦略思想が変化しています」と現代的な防衛概念を提示し、「防衛予算が増えて兵器も増えると、使いたくなるのが人情ではないでしょうか」と懸念を示しました。
川邊氏はトランプ氏の政策に対する日本の対応について2つの選択肢を提示しました。「1つは、トランプ氏が考える世界観に日本も順応して、国益に変えていくやり方」と説明します。
そして「トランプ氏の発想や変化の速さについていけず、戸惑っている政府が多いわけです」と分析し、「そういう人たちに対して日本がこれまで築いてきた民主主義的な価値観や、平和に対する考え方は強い安心感を与えると思います」と延べました。
「つまりもう1つの選択肢は、アメリカに左右されずに対応すればいいのではないでしょうか。アメリカは否定的に思うかもしれないが、他国からは日本への好意を獲得できるのではないかと思います」と戦略的な選択肢を示しました。
両顧問からのメッセージ
講義の最後に、村上氏と川邊氏から投資部と政治部の部員及び両部へ興味を持っている生徒たちに向けてメッセージが送られました。
村上氏は自らの体験をこう語ります。
「投資を怖がってください。本日の事前質問でも『村上さんは怖くないのですか』という内容がありました。私も昔は恐怖を感じていました。最も恐怖を感じたのは、自分が大きな利益を得た翌日からストップ安が3日間続いた時です。小学生が100万円を受け取り、大きな投資を行い、250万円にした瞬間から毎日40万円ずつ下落した時は、本当に恐怖でした。怖くて、手放してしまいました」
そして最も重要なメッセージとして、「失敗を経験していただくために投資部特別顧問の活動を行っています。損失を出した時の恐怖心、もう投資をやめてもいい、二度と投資をしたくないと思っても構いません。経験が大切だと考えているため、ぜひ怖がってください」と述べました。
川邊氏は講義を振り返り、「前半はAIの話、後半はトランプ氏の話ということで、これは対極的な内容でした。テクノロジーの塊の話と、人間の塊の話、この2つが現在同時に起こっており、一言で表現すれば『熱い時代』だと感じています」と表現しました。
そして生徒たちに向けて、「2020年代はコロナから始まり、どのような展開になるか予想がつきませんでしたが、不透明感は強いものの、非常に熱い時代だと考えています。このような熱い議論ができる中学・高校は素晴らしいです。N高グループの皆さんは、それに幸せを感じて、大いに議論して自分なりのアクションをどんどん取り、この熱い時代に自分なりの主張を響かせてもらえばと思います」と励ましの言葉を送りました。
この講義は、現代の重要課題について生徒たちが主体的に考え、議論する機会となりました。生成AI、円安、トランプ大統領の政策という一見異なるテーマを通じて、テクノロジーの進歩、経済の構造変化、国際政治の複雑さという本質的な課題が浮き上がってきました。
両顧問の実体験に基づく議論と、生徒たちの率直な質問や意見により、生きた知識と思考力を育む場となりました。N高グループの投資部と政治部が目指す、実践的な学びと主権者教育の理念が体現された講義となったと言えるでしょう。
生徒たちの学びと気づき
【投資部】
S高2年 吉田 朱希さん
今回の講義で、私は無意識のうちに「自分や日本にとって良いか悪いか」という前提で物事を判断していることに気づきました。村上さんがトランプ政権の関税政策を「アメリカ国民にとってどう映るか」という視点で捉えていたように、相手の視点から物事を読み解く姿勢が重要だと学びました。
これは川邊さんが話された生成AIにも通じます。生成AIそのものではなく、使う人間のあり方こそが恐怖の本質という話は、自分の不安の背景を掘り下げるきっかけになりました。投資も思い込みや感情に左右されやすいため、前提を意識し、視点を変える訓練が大切だと実感しています。
N高2年 吉川 玲さん
村上さんと川邊さんの講義は、挑戦や決断の中にいる私たちにとって心に残るものでした。特に印象的だったのは、トランプ大統領の政策について川邊さんが迷わず「賛成」と手を挙げ、「たくさん動いている人を止めるのは、ものすごくエネルギーがいる。だから放っておいたほうがいい」と語った場面です。これは、リスクを冒してでも動こうとする人たちへのエールのように感じました。「挑戦してる人って、面白いじゃん。実験として見てるとさ」という言葉も、そのスタンスを象徴していました。
一方、村上さんは投資部の生徒たちに「怖がれ」と呼びかけました。投資の世界で恐れや不安を感じるのは当然であり、それは本気で取り組んでいる証拠だと。怖がらずに進む方が危険なのかもしれません。
お二人の言葉は異なる角度でしたが、「まず動いてみる」「本気で向き合う」という共通の姿勢がありました。この学びを今後の挑戦につなげていきたいです。
【政治部】
N高2年 金子 由幸さん
合同講義で最も印象に残ったのは「多角的な視点からものを見る大切さ」です。特に「トランプ新大統領の政策」について興味を持ちました。
トランプ大統領の政策は世界に影響を与えています。多くの方が関税政策に注目する中で、私は「政府効率化省」に焦点を当てました。この機関は予算支出の削減や政府の規模、財政赤字の縮小を目指します。政治的視点では小さな政府の実現に近づき、経済的視点では歳出削減により財政赤字が縮小すると考えられます。このように、一つの視点だけでなく複数の多角的な視点から物事を見ることで、新しい発見があり、視野を広げる重要性を改めて実感しました。
村上さんと川邊さんから直接意見を聞き、質問できたことはとても有意義でした。今後もこのような講義があれば参加したいです。
現在、私は個人で「SNS問題」や「地政学」などを研究しており、今回の学びを生かし、多角的に物事を捉えることを大切にしていきたいです。
S高3年 東坂 明憲さん
合同講義は私にとって未知の領域に踏み込む体験でした。村上さんと川邊さんの議論や見解は、私の価値観に新たな視点を加えてくれました。特に印象的だったのは、トランプ氏の政策について「進むと決めている人に歯止めを掛けるのが最も不毛であり、良い事・悪い事とも本人が実行して身をもって結果を実感するのが一番良い」というお二人の考え方です。
村上さんは「彼は”儲け”に興味があって、戦争を助長するタイプの指導者ではない」と分析しました。この言葉を通して、型破りな指導者であっても、直接的に世界平和を脅かさない限り、強引に歯止めをかける必要はないという考え方を学びました。
トランプ氏をはじめ、各国の指導者にはそれぞれ目指す”ユートピア”が存在します。日本のリーダーを志す私にとっては、他国の理想を尊重しながら、協調と発展を基盤とする日本人らしい「ユートピア」を表明する必要性を感じました。これは今後の考え方を支える大切な指針となります。
【一般 学園生】
S高1年 大屋 諒さん
合同講義に参加して、いかに自分のニュースを見る視点が狭かったかを痛感しました。特に、トランプ大統領の政策に対する賛否の議論は衝撃的でした。
それまで私は、トランプ大統領の政策の意図が理解できず、なぜそのような方針が取られるのか疑問に思っていました。しかし、お二人の「トランプ氏が行っているのはアメリカ国民のための政治であり、他国の利益よりも自分たちを優先するのは当然」という話を聞いて、目から鱗が落ちる思いでした。これまで全く想像もつかなかった切り口であり、深い洞察力と経験を持つお二人がニュースや時事問題をどのように捉えているのかを垣間見た気がします。
今回の講義で得られたものは、問題分析や考え方だけにとどまりません。何より大きかったのは、自分が想像もしなかった視点から物事を見る重要性に気づけたことです。これまでは表面上の出来事だけに目を向けがちでしたが、その背後にある「なぜそうなったのか」「誰にとってどんな意味があるのか」といった背景や意図にこそ注目すべきだと感じるようになりました。立場の違いや価値観など、多くの視点を組み合わせて問題を掘り下げることで、理解の幅が広がることを実感しています。今回学んだ視点を糧にニュースや社会課題に積極的に向き合い、いつか自分もお二人のような広い視野を持つ大人になりたいです。
N中等部2年 安部 愛禾さん
合同講義に応募したのは、投資部・政治部の顧問のお二人に直接質問できることに魅力を感じたからです。部活には所属していませんが、滅多にないチャンスだと思い参加しました。当日、お二人の意見からたくさんの刺激を受けました。
講義では、賛成・反対をどの立場で考えるかで物事の見方が大きく変わると感じました。どちらとも言い切れない意見を統合するのは難しかったです。考えを深める中で、日頃から時事問題に積極的に触れることの大切さを実感しました。お二人が私見の根拠として日常のエピソードを挙げていたからです。ニュースや社会問題に真摯に向き合っている姿勢が伝わり、私はこれまでニュースに深く関わらず、視野の狭い生活をしていたことに気づかされました。
今まで時事問題について考え発表する機会も、その重要性も意識したことがありませんでした。しかし、たとえ直接生活に影響を及ぼさないテーマであっても、進路などの大きな決断をする際には、その経験の有無が大きな違いを生むと感じています。これからは時事問題を自分の中に取り込むことはもちろん、他人ごととして放置せずに、積極的に理解していこうと思います。
最後に
生徒たちが政治や社会課題と真剣に向き合う貴重な機会となりました。この経験が、今後の活動や未来の可能性を広げる一歩になることを期待しています。
■投資部 https://nnn.ed.jp/club/investment https://x.com/n_investors
■政治部 https://nnn.ed.jp/about/club/politics/
合同講義の模様はこちらからご覧いただけます。
ニコニコ生放送:https://live.nicovideo.jp/watch/lv347535147
YouTube:https://www.youtube.com/live/QaJFjb0Lz_8
X:https://x.com/i/broadcasts/1kvJpypZZLkxE