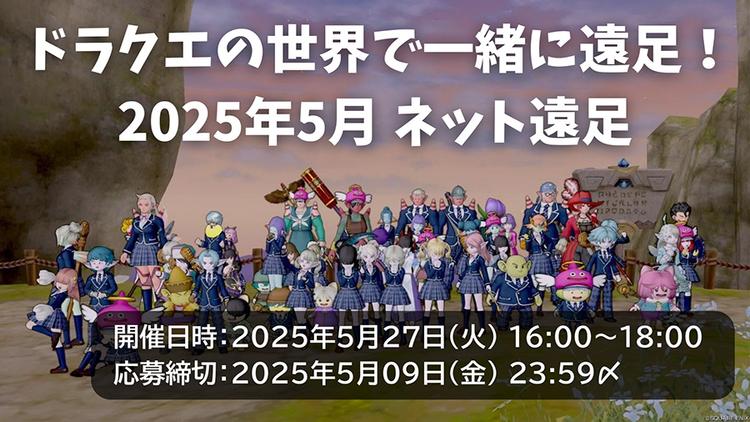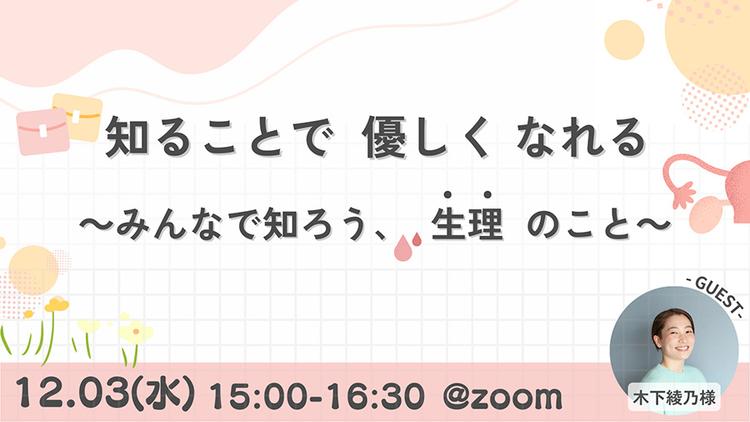2020年9月より新たに発足したN高政治部。政治家と直に触れ合う機会を持つことで、政治を身近に感じてもらうと共に、正しいメディアリテラシーを身につけ、自分で考え判断できる力を持った主権者となることを目指します。著名な政治家をゲストに招いた講義が順次開催され、早くも多くの学びを得ている政治部メンバーたちです。
※N高政治部については、こちらのニュースからもご確認いただけます。
「N高政治部」を設立~特別講師に三浦瑠麗氏が就任~ 9月9日、初回授業に麻生副総理が登壇
※ここからの内容は、政治部部員の生徒に書いてもらいました。
今回のブログでは、政治部特別講師である国際政治学者の三浦瑠麗さんによるオリエンテーション講義の内容をまとめ、自身の学びのアウトプットとしてもご紹介したいと思います!


■自助努力とは
今回三浦さんがテーマとしたのは、菅義偉総理が総裁選で掲げた社会像「自助・共助・公約」をめぐる意見の対立。
菅総理が総裁選における公約に「自助、共助、公助、そして絆」を理念として掲げたのに対して、立憲民主党の枝野幸男代表が「自助や過度な自己責任ではなく支え合う社会をつくる」と批判的な発言をした件を掘り下げ、政治の持つ一面について解説してくださいました。

最初に、三浦さんから生徒に向けてこんな問いかけがありました。
「菅総理が総裁選で話した内容をすべて聞いた人?」
この質問に対して手を上げた生徒はたった一人でした。
この時点で、私たちが聞いている・見ている情報というのはすでに切り取られているものだということが分かります。
枝野代表の発言はニュース媒体、あるいは評論家のテーマに沿って取り上げられた一部分であるということです。
さらに、時事通信社の記事によると、
新立憲民主党の枝野幸男代表が、自民党の菅義偉総裁が掲げる社会像「自助・共助・公助」の「自助」を批判していることをめぐり、過去に自らも言及していたことが15日分かった。2005年に国会で「生活保護はまさに自助・共助・公助だ」と発言した。枝野氏が官房長官だった11年に政府・与党がまとめた税と社会保障一体改革の文書にも「自助・共助・公助の最適なバランスで支えられる社会保障制度に改革」との記載があった。 (2020年9月15日)
とのことでした。
この事実を知ると、枝野さんは菅さんと同様の考えを持っていたことがわかります。もちろん、この記事自体も内容が切り取られている可能性があるため、三浦さんが全文を読んでくださいました。
しかし、全文を聞いた後でもやはり二者間における「自助・共助・公助」に対する大きな考えの相違は見て取れません。これはつまり、そこに大きな意見の違いはないけれど、与野党間に対立が生まれているということです。
わかりやすい例として消費税を取り上げます。「消費税に賛成か反対か」というような大きな問題自体であれば多数決が取れますが、消費税の裏にある問題として、誰にどのように負担してもらうのか、あるいはどのぐらい国は借金をして良いんだろうかという考え方については、賛成派でも反対派でも大して変わらない可能性があるということです。

ここまでのポイントは4つあります。
1.発言は切り取られる
2.政治に関心がある人であっても発言全文を読むことはない
3.枝野さんは主張の力点を変えることで菅さんと違う切り口をアピールした
4.枝野さんのかつての発言や文書によると、菅さんと似たような意見を持っていたことが分かる
これらを踏まえると、政治における発言や主張、情報というのは、誰かの意志や立場によってフォーカスされる部分が異なるということです。すると、伝わるメッセージも異なってきます。それこそが政治におけるメッセージングであり、政治家やメディアによって意図的に活用されている場合もあるのです。
■自分のアタマで政治を考える
このように、講義では私たちが気づかなかった視点を、データを元に教えていただきました。
若年層と高齢者層の考え方の違い、日本人の価値観、平等と公平に関する問題など、他にもさまざまなテーマが取り上げられました。身近な話題に触れながら多くの学びと、考えるきっかけをもらえるお話です。
※YouTubeで全編をご覧いただけますので、こちらも是非チェックしてみてください。
【N高政治部】三浦瑠麗 特別講師 オリエンテーション講義:https://youtu.be/YfFr6Nv9wMg
今回の講義の終着点は、「政治を考える上では先入観を廃することが必要」ということです。そのためにはまず関心を広げると同時に、「自分のアタマで政治を考える」ということが大事になります。
■私たちは自分のアタマで政治を考えられているか?
政治といえば国会で言い争っているというようなイメージがありますが、実際に国や制度をより良くしていくためには、先入観で考えることなく、データや正確な現状把握、理想の構築などを元に考えていく作業が大事です。
しかし、多くの人々は正確な現状やデータも、自分の理想もあまり考えていないと思います。それは政治に関心がある人も、ない人も同じです。
メッセージングや先入観で単純に“YES”or“NO”と答えを出すのではなく、しっかりと自分のアタマで政治を考えようと思えた初回オリエンテーション講義でした。