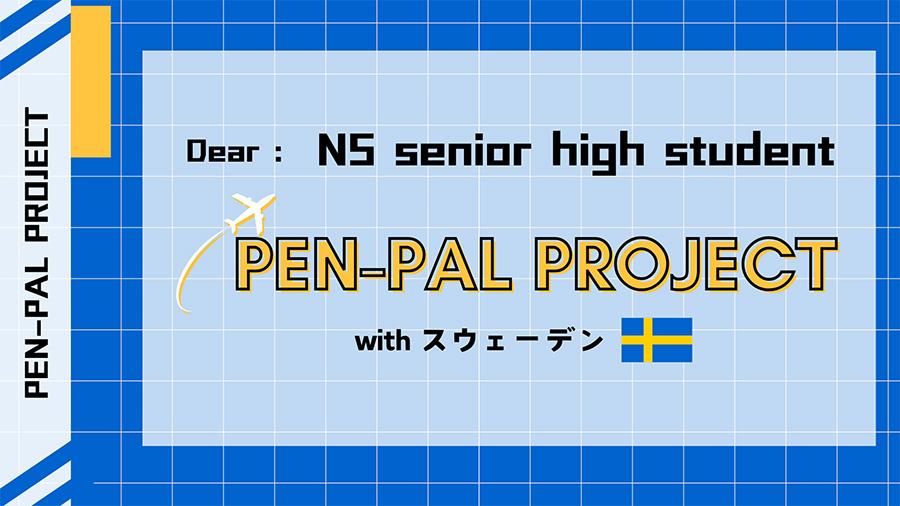
※このブログは、通学コース2年生・坂口 祐華さん、ネットコース2年生・中村 匠さん、通学コース2年生・大橋 彩美香さん、通学コース2年生・木村 優希さんに書いてもらいました。
9月から11月にかけて、NS PenPal Projectの実施をしました。
このプロジェクトは国際交流を目的としたオンライン上での文通プロジェクトです。
参加者には手紙をオンラインで作成し、外国語学習課とつながりのあったスウェーデンの高校と英語で国際交流をしました。
■企画のはじまり
2024年7月に集まったプロジェクト(pj)メンバーで企画設計が始まりました。生徒会メンバーとサポートメンバーの8人で始まったこの企画は職員のサポートを受けながら、生徒主体でターゲット設定から参加募集告知資料の作成まで全員で協力しながら行いました。
私たちが初めにつまずいたのは、手紙の形式部分でした。参加者が1人1通の手紙を書いてもらう形式と数人のグループで1通の手紙を書く形式の2つをそれぞれメリットとデメリットを挙げて検討しました。ターゲット層に適した効果的な方法や実現可能性などから議論し、数回のミーティングに渡ってイメージを擦り合わせて行きました。
最終的には1人1通書くことにし、作成の課程で参加者同士が話し合い、相談し合える環境も作るという両者の利点を併せ持った形式を採用することになりました。スウェーデンの学校の状況をよく知る職員から情報を、生徒会メンバーから考え方や視点を、サポートメンバーからは参加者のフラットな視点をそれぞれ合わせられたことでよりよい選択肢を取ることができたのではないかと思います。
■事前準備
企画の方向性が決まった後は、参加生徒の募集に向けて準備を進めました。
告知をする上で、ターゲットに向けてどのようなアプローチにするかをよく考えて告知用スライドを作成しました。
今回のワークショップでは、英語初心者の方を主に対象として実施しました。初心者の方にも来てもらいやすいようにするため、スライドを使ってワークショップの敷居が高くなるのを防ぐことを意識しながら、告知資料の作成にあたりました。

特に難しかった部分として、参加者がZoomに集まり、相手校への手紙を同時に書くというレターセッションの流れをどのように説明したら分かりやすいか、という話し合いを何回も行い、改善を重ねました。
私たちも手紙をオンラインで送り合うというのは今までになかった経験だったため、参加者側の目線で常に考えながら事前準備を行いました。オンラインで手紙を送る際、手紙の提出をGoogleドライブを通して行うことにしたため、そこでも分かりやすくスライドや動画を用いて説明を行いました。
また、手紙を作る際、自分でデザインを作るのはハードルが高いのではと思い、サポートメンバーで手紙のフォーマットの作成をし、デザインをするのが苦手という方でも、安心してプログラムに挑んで頂けるようにしました。
告知をする前までは、応募してもらえるかな...ととても心配でしたが、情報解禁から2日という短期間で定員に達し、嬉しい限りでした!
■イベント当日の様子
イベント当日は、オンラインミーティングソフト「Zoom」を活用して、参加者とサポートメンバーでネットに集って行いました。当日はスウェーデンの学校とN/S高から集まった参加者20名と、企画メンバー、そしてサポートとして外国語学習担当の教職員にも参加いただきました。
私は相手校所在地のスウェーデンに近いエストニアから参加しました。このように日本のみならず海外からも繋がることができる点がネットの高校の強みで、N高グループならではだと思います。参加者も、日本全国いろいろな場所から参加していました。相手校への手紙送付も、Googleドライブを活用して、参加者一人ひとりにフォルダを作成し、同じ人とやり取りできるように工夫して行いました。
いざセッションが始まると、まずはプロジェクトの説明から始まりました。参加者は全員とても興味津々な様子で、真剣な眼差しで説明を聞いていました。サポートメンバーは事前準備の成果を発揮すべく、参加者にわかりやすく説明することを第一に奮闘していました。説明が終わると、アイスブレイクを通じて参加者同士で交流しました。自己紹介代わりに行う出来事紹介、もし〜できたらどうする?という妄想自己紹介などオンライン上でできることを通じ、参加者同士交流することができました。
手紙の作成に入ると、ブレイクアウトルームというZoomの機能を活用し、静かに作業する部屋、参加者・サポートメンバー・生徒会役員と話しながら書くことができる部屋、BGMを流す部屋など、さまざまな選択肢を用意し、参加者がどういった環境で手紙を書くか決めて、自分で選んだ環境で真剣に手紙を作成していました。
私は話しながら作業する部屋に参加しました。セッション中はヨーロッパに滞在していたので、相手校の雰囲気に近い現状をZoom越しで参加者に共有することができました。国際交流や留学などに興味がある人がとても多いので、自分の経験や将来像について話したり、日常のたわいもない話しなど色々することができて、とても良い雰囲気の作業部屋となっていました。
このイベント当日の参加を経て、参加者は、手紙を相手校に送信する締め切り日まで各自手紙の作成に取り組みました。完成した手紙はどれも内容が充実したものばかりで、参加者にとっても学びになる要素が多く、さらには楽しんで国際交流ができるというメリットしかありませんでした。
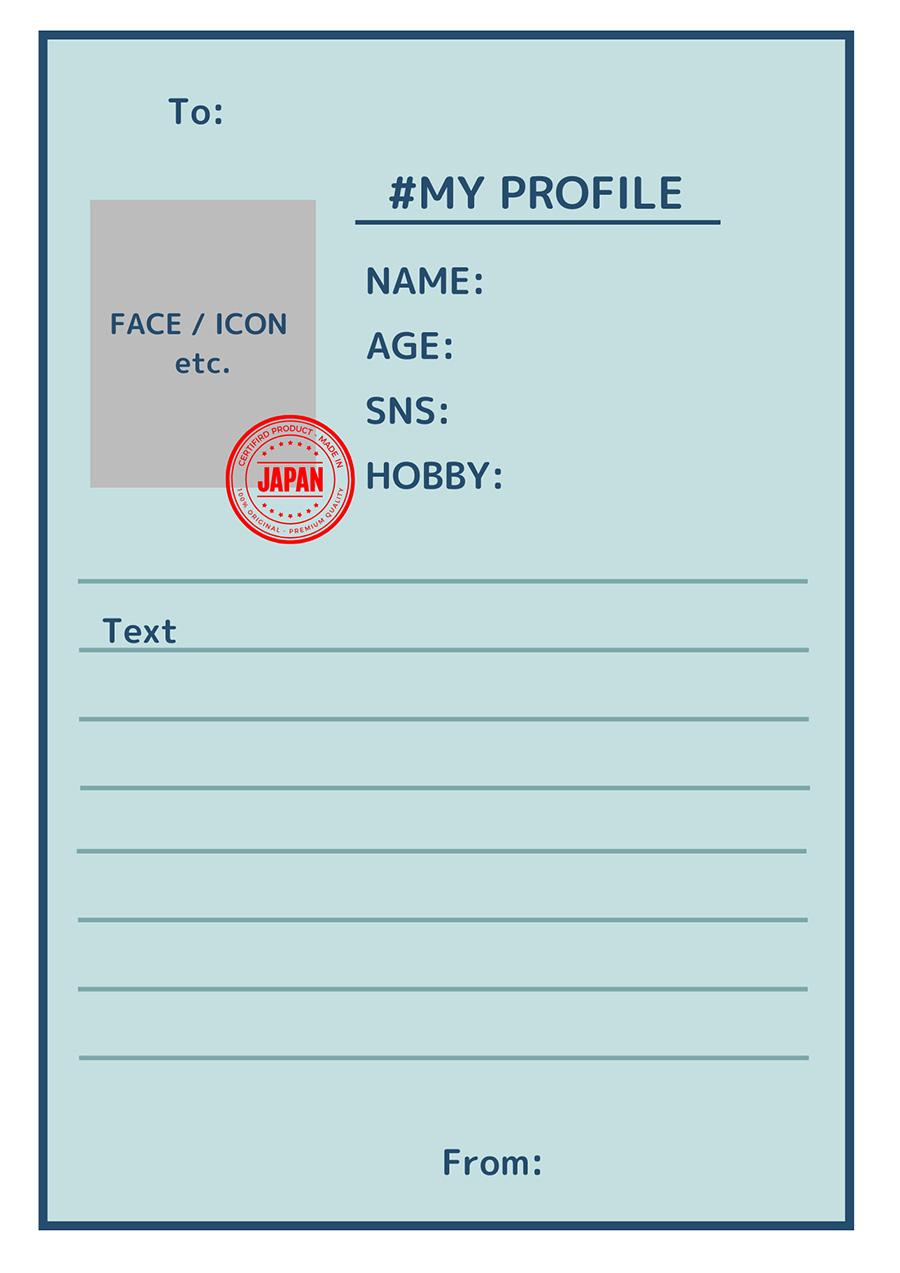
企画メンバーは、相手校との事前擦り合わせや参加者募集など活動の初期段階から、少ない人数の中で、一人ひとりが持っているスキルや想いを共有して、プロジェクトにしっかりと反映することができました。
自分がレベルアップしたのはもちろん、全体を通して学びになることがとても多かったと思います。
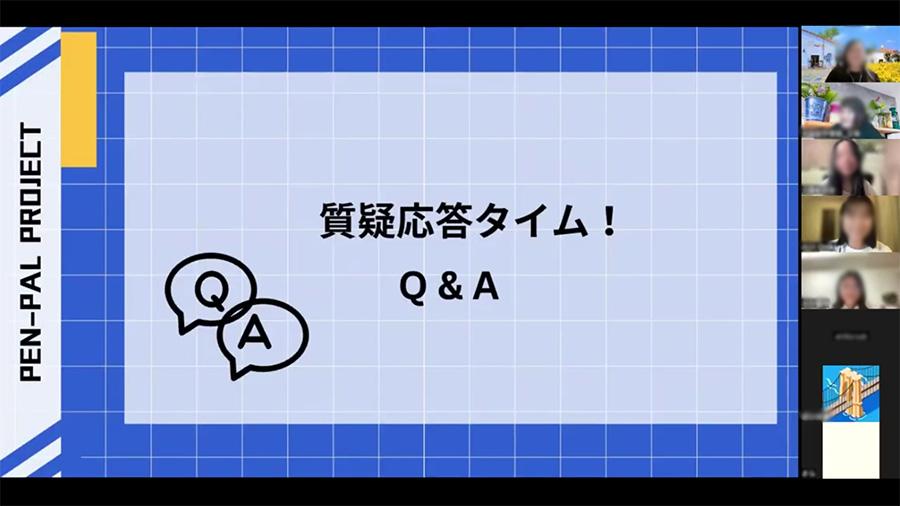
■振り返り
今回のプロジェクトは、海外の同年代と交流することができるとても貴重な機会でした。
参加した生徒はみんな、とても熱心に取り組んでいました。
全国各地から英語レベルや国際経験に関わらず、幅広い人が参加してくれたこと、そして手紙のデザインや内容で自分らしさを出すことで、手紙の利点を最大限活かすことができました。
終了後は参加者の方から「共通の趣味で話が盛り上がった」「お互いの国の文化や暮らしについて話せて面白かった」などの感想を聞くことができ、とても嬉しかったです。国際交流の一助になれたようで、このプロジェクトの運営に参加してよかった、と心から達成感を味わいました。
また、企画を通して、約8000kmも離れたスウェーデンを身近に感じることができ、英語は「教科」ではなく、世界とつながることができるコミュニケーションツールであることを実感しました。「企画運営側も手紙交換に参加したい!」と話してしまうほど楽しく、多くを学べた企画でした。
今回は貴重な機会をいただきありがとうございました。
企画の進め方やコミュニケーションの仕方など、学んだことを今後に活かしていきます。
▼N高グループ 生徒会について
https://nnn.ed.jp/about/seitokai/



